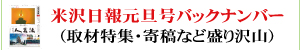|
『初代伊達政宗の置賜地方侵攻について』 渡邊敏和
寄稿者略歴

渡邊敏和(わたなべ としかず)
昭和31年、山形県東置賜郡川西町上小松生まれ。山形県立長井工業
高校卒業。平成17、18年、川西町獅子頭展実行委員長。 置賜民俗
学会理事。
はじめに
令和7年5月のある日、川西町フレンドリープラザ内の町立図書館で司書の遠藤副館長から伊達氏と置賜を領した長井氏との戦いについて聞かれたことがあった。
戦国時代、奥州制覇を目指した独眼竜政宗は、先祖で有名な先代儀山政宗の名を受け継いだものである。伊達氏が出羽国(現在の山形県)置賜郡に侵攻したのは、南北朝時代の康暦二年(北朝年号・南朝は天授六年・1380)であると謂われている。伊達8代当主の宗遠(嫡子が9代の儀山政宗)が、長井荘(正式名は置賜郡)の地頭である長井(本姓大江氏)道広を攻めて同荘を略奪した。伊達氏の侵攻については当時の資料がなく分らないことが多い。それで後世の資料などで推測してみた。
一、伊達氏の置賜進出
伊達氏の置賜侵攻は、「伊達正統世次考 」巻之四(原本は漢文、編纂は江戸時代の元禄十年から十五年ころと推定・1697~1702)で伊達宗遠(1323~85)の項に次のように記してある。
「甞(かつ)て父君(行朝)之志を継ぎて。忠を南朝に於(おいて)致(いた)し。近郡及び近国を伐(うっ)て。或は城を抜き、地を取り、或は之を下す。長井掃部頭(かもんのかみ)入道道弘(どうこう・8代廣房の道号)を、其(その)地出羽国置民(置賜)郡長井荘を取り、而して之に入る。時、鎌倉の管領持氏朝臣。京都将軍の命を奉(ほう)じ。近国の諸将に令して曰く。道弘本領羽州長井の荘以下所所。嚮(さき)己に京都の命を以て遵行し。伊達の悪党を退け了(おえ)る。然と雖、彼の輩(やから)重(かさね)て違乱す可(べ)きを聞く。早く道弘に於(おいて )、力を合わせて其をして全く之を知行令(せし)む可しと云々。文書に見えたり。是れ小沢伊賀守某に与る書に見る。七月廿五日と書し年号無し。今、家臣安田氏之を伝ふ。」
とあり、伊達宗遠が置賜を本領する長井道広を攻めて、押領した。
それに対して、鎌倉管領(公方)の持氏(祖父の氏満ヵ)が京都室町の足利将軍の命を受け、近国の諸将に対して道広への援軍を命じて伊達氏を退却させたが、再び伊達氏が乱入した。早く道広に協力して知行地を保てと文書に記す。
長井道広は永和四年(天授四年・1378)に鎌倉公方の足利氏満の評定衆頭人となっている。(「喜連川判鑑」)また、山形を代表する近代の郷土史家で米沢の伊佐早謙(1857~1930)が著した「奥羽編年史料」に次の記述がある。「康暦二年十月、伊達宗遠が長井広房を攻め、出羽国置賜郡長井荘を攻略し所領とした。二十五日足利氏満が傍近の諸将に命令し、広房を援けさせたが及ばず。この戦争で広房の将新田某戦死す。広房は遂に其の邑置賜長井を失う。広房は禅を信じ抜隊得勝禅師に参得し道広と号した。」この2つの史料の記載で、康暦二年(天授六年・1380)十月に伊達宗遠(当年58歳)が侵攻して置賜郡を奪い取ったというのが定説となっている。同じく「伊達正統世次考」巻之四には、「 於石田左京亮(すけ)知行配分之判状を賜う。其文に曰く。出羽国置民(置賜)郡長井荘。鴇谷(ときや・川西町時田の吉田東伍説と長井市時庭の伊佐早謙の二説あり)郷内一宇、乗観跡一宇、小瀬入道(雑給、藤九郎跡)一所(中略)右配分之状如件。康暦二年十月八日。石田左京亮殿。沙弥、書判(宗遠花押 )」と文書の記載があり、続く石田左京亮の補足文に、「( 前略 )蓋是年遂亡長井入道道広。取其地以配分之賞其功臣也。」と記される。
 また、成島八幡神社に伝わる永徳三年(南朝・弘和三年・1383)の棟札には、「奉造立、大壇越弾正少輔藤原朝臣宗遠、永徳三年六月一日、成嶋庄八幡宮拝殿、別當阿闍梨金剛者」と記されており、米沢地域を伊達宗遠が勢力下としていることが分かる。
また、成島八幡神社に伝わる永徳三年(南朝・弘和三年・1383)の棟札には、「奉造立、大壇越弾正少輔藤原朝臣宗遠、永徳三年六月一日、成嶋庄八幡宮拝殿、別當阿闍梨金剛者」と記されており、米沢地域を伊達宗遠が勢力下としていることが分かる。
(写真左=宮城県七ヶ宿町の東光寺)
この年に、陸奥国伊達郡の東昌寺を置賜郡永井庄米沢郷夏刈に移した。(仙台、「東昌禅寺」記録 )。このころに、同じく伊達郡に建立された伊達3代義広の菩提寺観音寺も夏刈村に移した。
 伊達宗遠は、亘理肥前守行胤と刈田で戦い、亘理氏を麾下に属す。大崎から二郡を取り、信夫、刈田、柴田、伊具を服従させる。だが、先の「伊達正統世次考」巻之四には、「今按ずるに系図及び世に伝へ言ふ。政宗公の時、始て長井の荘を取ると。因此文書。及下所載永和二年(1376)。康暦二年の文書に、則(すなわち)公(政宗 )之を取れる也。而謂之政宗公者思。為儲嗣親往撃顕其功也。」として宗遠の嫡子である儀山政宗が置賜を領したとの記述もある。
伊達宗遠は、亘理肥前守行胤と刈田で戦い、亘理氏を麾下に属す。大崎から二郡を取り、信夫、刈田、柴田、伊具を服従させる。だが、先の「伊達正統世次考」巻之四には、「今按ずるに系図及び世に伝へ言ふ。政宗公の時、始て長井の荘を取ると。因此文書。及下所載永和二年(1376)。康暦二年の文書に、則(すなわち)公(政宗 )之を取れる也。而謂之政宗公者思。為儲嗣親往撃顕其功也。」として宗遠の嫡子である儀山政宗が置賜を領したとの記述もある。
(写真右=東光寺にある伊達九代政宗儀山の墓)
二、儀山政宗の置賜の領有など
 儀山政宗が置賜を領したという資料には、江戸時代の元文元年(1736)の地誌書「米澤事跡考」と、享和元年(1801)に、国分威胤により著された「米澤里人談」、同時期の「米澤鹿子」、文化元年(1804 )に小幡忠明「米澤地名選」もほぼ同じで、次のように記されている。
儀山政宗が置賜を領したという資料には、江戸時代の元文元年(1736)の地誌書「米澤事跡考」と、享和元年(1801)に、国分威胤により著された「米澤里人談」、同時期の「米澤鹿子」、文化元年(1804 )に小幡忠明「米澤地名選」もほぼ同じで、次のように記されている。
(写真左=新田氏の家来を祀る長井市歌丸にある6基の板碑)
 「新田墓、下長井歌丸村の野中に有相傳て云至徳の比(1384~86)伊達政宗大軍を卒し北条郷に屯す長井出羽守は新田遠江守を将として、小松村邊(西大塚菊田の陣ヶ峯)に出張す伊達偽りて和を乞ひ白川の滸(ホトリ)に会盟す新田慢りて甲兵の備なし一族従者少長となく生捕われ或は誅せらる其後伊達長井を掌握して新田か霊を薦め此所に法會を設け墓を封し五輪石を建。」である。新田遠江守の墓とされる五輪塔が、元歌丸の窪にあったが、近年、同じ歌丸(現在、長井市)の金鐘寺境内に移された。その新田氏の家来を祀るという6基の無銘の板碑「六本仏」が同じ歌丸のJR米坂線踏切の西方に建っている。(写真=新田の塔の案内看板)
「新田墓、下長井歌丸村の野中に有相傳て云至徳の比(1384~86)伊達政宗大軍を卒し北条郷に屯す長井出羽守は新田遠江守を将として、小松村邊(西大塚菊田の陣ヶ峯)に出張す伊達偽りて和を乞ひ白川の滸(ホトリ)に会盟す新田慢りて甲兵の備なし一族従者少長となく生捕われ或は誅せらる其後伊達長井を掌握して新田か霊を薦め此所に法會を設け墓を封し五輪石を建。」である。新田遠江守の墓とされる五輪塔が、元歌丸の窪にあったが、近年、同じ歌丸(現在、長井市)の金鐘寺境内に移された。その新田氏の家来を祀るという6基の無銘の板碑「六本仏」が同じ歌丸のJR米坂線踏切の西方に建っている。(写真=新田の塔の案内看板)
 また、成島八幡神社に伝わる明徳元年(南朝・元中七年・1390)の棟札には、「 奉造立、大壇越大膳大夫藤原政宗、別當律師金剛佛子宏範、明徳元年庚午十月八日、若宮別當圓耆、成嶋庄八幡宮門神御殿、大工藤内左衛門尉家吉」と記されてあり、伊達宗遠、政宗親子が地域の有力な八幡信仰を保護して土豪、地域民に領主が長井氏から伊達氏に代ったことを知らしめた。
また、成島八幡神社に伝わる明徳元年(南朝・元中七年・1390)の棟札には、「 奉造立、大壇越大膳大夫藤原政宗、別當律師金剛佛子宏範、明徳元年庚午十月八日、若宮別當圓耆、成嶋庄八幡宮門神御殿、大工藤内左衛門尉家吉」と記されてあり、伊達宗遠、政宗親子が地域の有力な八幡信仰を保護して土豪、地域民に領主が長井氏から伊達氏に代ったことを知らしめた。
(写真左=新田遠江守の墓、長井市歌丸の金鐘寺)
また、川西町上小松の諏訪神社に伝わる社記には、
「暦仁年中(りゃくにん・1238~39)大江時廣之を造営し、其七代の孫大江廣房に至る迄維持修築せり。至徳(1384~87)伊達政宗深く之を崇奉して社宇を造営し、(同三年)社領若干を附す 。」とも地域の社寺を崇敬して地域の土豪、領民を慰撫するなどして安定を図った。
さらに、本拠の伊達郡から桑折、大町、原田、国分氏など一族や配下の武将に置賜郡内の知行を与えたり、長井氏に与していた船山、大塚氏など土着の有力土豪たちも伊達氏のもとに支配を強めている。
たとえば、嘉慶二年(北朝年号・南朝は元中五年・1388)七月四日の国分文書の「伊達政宗知行配分状」には、次のように記されている。表書きに「九世政宗公東光寺様御判物」とあり、
「出羽国置民(賜)郡、長井庄、萩生郷内、四十九貫八百四十八文、当分限云々、右所配分之状如件、但本配分状不請取之由候之間、遂任本目録、判行候畢
嘉慶二年七月四日 兵部権少輔(花押)
国分彦四郎入道殿 (伊達儀山政宗)」
 と書かれている。
と書かれている。
(写真右=舘山寺、米沢市、写真 米沢日報デジタル)
前に記した地誌書「米澤事跡考」には、古舘の項に「新田城」の記載があり、それに、「新田城は上長井田澤村に有。奥州佐藤基行か弟泉の十郎清綱か孫、新田冠者藤原経衡か居城也。苗裔数世氏に属す。新田遠江守、同美濃守に至て、伊達氏の為に家滅没す。明徳の比、伊達氏新田の遺跡を立て、其子孫、天正年中(1573~92)に新田安房守と云、舘山村旗本山舘山寺曹洞宗の開基。此寺に碑有り。舘山寺殿虎山威公居士、永禄元壬辰年(1558)九月二日卒す。」
とある。このことから、白川の戦いで戦って滅ぼされた新田遠江守の子孫も数年を経ず明徳年中(1390~94)に伊達氏の家臣として取立てている。
それ以後も儀山政宗代には、周辺の武将を攻め立て、新たに黒川、亘理両氏を服従させ、名取、宮城、深谷、松山(宮城県内)、宇多(福島県 )の諸郡の武将を服属させた(伊達家譜)とあり、伊達氏の版図を著しく拡張させている。
三、儀山政宗の関東管領との戦い
足利二代将軍義詮が弟の基氏を鎌倉に関東八か国を統括する関東管領(関東公方)に任命する。義詮の嫡子で三代将軍義満は明徳二年(1391)に奥羽両国もその統括下に置いた。
応永四年(1397)、政宗は、嫡子の氏宗と共に上洛して将軍義満に拝謁した。その政宗室紀氏「法名・輪王寺殿蘭庭明玉尼大姉」は石清水善法寺通清の女で、義満の母紀良子と姉妹で叔母に当る。政宗は足利将軍と縁戚となっている。同六年に至ると、前年に死去した関東管領足利氏満の跡を継いだ満兼が弟二人を奥州に送り篠川(郡山市)、稲村(須賀川市)両御所で政務を取らせ、京都室町将軍が任命した奥羽両探題の大崎、最上両氏を鎌倉に留めて権限を弱めて京都の将軍と対抗した。
関東管領から関東、奥羽の諸将に対して奥州御所御公地として領地を進上するよう迫られた。政宗は置賜郡から北条三十三郷を進上すると申しいれたが、庄などではなく郡(置賜郡)を重ねて進上せよと迫られ、政宗は関東管領への反発を強くした。同七年に至り伊達政宗は五百騎の軍勢で、奥州探題の大崎氏とともに京都の将軍家の権威を守るため挙兵した。しかし、鎌倉方の白河の結城満朝は三千騎の兵により政宗は信夫庄まで追い込まれ、出羽へ逃げた。
大崎は仙道大越(田村庄)で切腹して果てたという。その後も政宗の反逆は続き、同九年には篠川御所足利満貞は、伊達儀山政宗を退治するために、上杉氏憲(禅秀)が下向し、5月21日に鎌倉を出陣し、赤館(福島県桑折町西山城)で合戦が行なわれ、9月5日に負けて降参したとも(「鎌倉大日記 」)、立て籠もる伊達軍に上杉軍28万騎は残らず討たれたとも(永正十一年・1514に成立「余目氏旧記」)、関東公方は三度も16~18万騎の大軍で征伐を試みたが、平定出来なかったとも(京都相国寺の瑞谿周鳳〈1392~1472〉の晩年の日記「臥雲日件録」)謂われている。
 (写真左=高畠城址に建つ石碑)
(写真左=高畠城址に建つ石碑)
儀山政宗は雪深く山々に囲まれた置賜の拠点として高畠城に住まいし、同十二年(1405)9月14日に、高畠城で儀山政宗は死去したと伝えられている。享年53歳。
法名「東光寺殿儀山圓孝居士」(「伊達正統世次考」)。
四、儀山政宗の和歌
儀山政宗は、父宗遠と同じく和歌をよくしたという。著名な政宗の和歌は次の二首で、
山家の雪
中々につゝら折なる道絶えて雪に隣の近き山里
山間霧
山合の霧はさなから海に似て波かと聞けは松風の音
右の歌については、「米澤事跡考 」では二首とも、米沢の舘山城に於いて詠んだものとして、「米府鹿子 」は、山家の雪は屋代峠の陣、山間の霧は高畠城を眺望して詠んだとし、「黒川郡誌 」は、山家の雪は板谷峠、山間の霧は屋代峠の作として、「東藩史稿 」では、鎌倉との和睦の際の作としており、諸説あって、どれが正しいのか明らかでない。この儀山政宗の名乗りを継いだ貞山(独眼竜)政宗も多くの和歌を作ったことで知られている。
五、儀山政宗の墓所
 (写真右=高畠町夏刈の儀山政宗の墓所)
(写真右=高畠町夏刈の儀山政宗の墓所)
高畠町夏刈に本拠の伊達郡から複数の菩提寺、寺院を移したことを記した。その夏刈には弘安年中(1278~88)に、屋代荘地頭長井氏三代時秀が鎌倉建長寺の紹規を招いて建立した約二百㍍四方の広大な寺域をもつ資福寺があった。現在はその跡を偲ぶ、内堀跡、観音堂跡とされる石祠がある。墓域には、儀山政宗夫妻の墓(五輪塔 )、夏刈城から足繁く資福寺に参詣したという伊達独眼竜(貞山)政宗の父輝宗と、殉死した重臣の遠藤基信の五輪塔も残る。資福寺は独眼竜政宗移封の後は仙台に移された。その儀山政宗の墓はもう一ヶ所、高畠町竹の森野手倉塔ノ峰にも儀山政宗夫妻(正面右塔が政宗の墓)の墓がある。
 (写真左=高畠町竹の森にある儀山政宗夫妻のの墓、右が政宗の墓)
(写真左=高畠町竹の森にある儀山政宗夫妻のの墓、右が政宗の墓)
その墓は、明治21年(1888)伊達家の家扶作並清亮が公墓の調査を命じられ、「正統世次考 」で、刈田郡湯ノ原山中に葬るとの記述を見て、湯ノ原鹿音山東光寺の記録を調べたところ、高畠城付近を地元協力者と捜索することになった。野手倉で長く荊棘の中に埋もれた古色蒼然たる五輪塔2基を発見し、政宗公の墓所なると判明した。同37年(1904)9月14日、伊達家では仙台から作並清亮を派遣し、屋代、高畠、湯ノ原の関係者が参列して政宗公の五百年祭を執行した。その時に墓所の周囲に石垣を施し、正面に二柱の墓標を建て、次のような墓銘を刻んだ。
(右)大膳大夫伊達政宗墓 應永十二年九月十四日卒
(左)伊達政宗室紀氏墓 嘉吉 二年七月二十日卒
その右、左の側面に、「明治三十七年九月十四日、二十二世孫従三位伯爵伊達宗基建」とある。
伊佐早謙の考察で、儀山政宗は高畠城に居り、同城在城中に卒去されて、法名「東光寺殿儀山圓孝居士」から屋代村根岸の東光寺領内に埋骨されたと考えられた。その後、東光寺は独眼竜政宗の仙台移封のとき、宮城県七ヶ宿町湯原に移った。
まとめ
これらを検討してみると、伊達宗遠のときに、置賜郡に本格的な侵略を始め、現在の米沢市、東置賜郡域を占領し、次の儀山政宗のとき、長井氏の重臣新田遠江守と戦い、戦いでは討ち破ることができず、和議を以って騙し討ちを仕掛け、それに新田遠江守は慢心にて、武具を携えず、一族郎党老若皆捕われ、大将を失った新田氏の軍勢は統率なく多くが戦わず討死、敗走した。敗れた長井道広は関東の所領に逃れ、これにより儀山政宗が置賜全域を領有した。
このことから、子孫の伊達輝宗は米沢城で誕生した嫡子に(独眼竜)政宗と名付けて伊達家の発展を期待した。因みに伊達氏に置賜を追われた長井道広は、先祖大江広元が得た武蔵国に逃れ、康応元年(南朝・元中六年・1389)同国横山に広園禅院を開基したという。(「広園開山行録」「八王子史」)。
引用・参考文献
・「山形県の歴史」(山川出版社 1998)
・新版「山形県の歴史散歩」(同前 1993)
・小林清治、山田舜「福島県の歴史」(同前 1970)
・「長井市史」通史編 第一巻 原始・古代、中世(長井市 2019)
・「川西町史」上巻(川西町 1979)
・「米沢市史」資料篇1(米沢市史編さん委員会 1985)
・米沢市史 資料第十五号「伊達正統世次考」(米沢市史編さん委員会 1985)
・長井政太郎「中郡村史」(中郡村史編さん委員会 1967)
・国分威胤、中村忠雄校註「米沢里人談」上巻( 置賜郷土史研究会 1966)
・石田勘四郎編「米澤古辞類纂 全」(盛文堂書店 1908)
・「東置賜郡史」下巻(東置賜郡教育会 1939)
・図説「山形県史」山形県史 別編Ⅰ(山形県 1988)
・小野榮監修、図説「置賜の歴史」(郷土出版社 2001)
・小野榮監修、決定版「置賜ふるさと大百科」(郷土出版社 2007)
(2025年6月16日19:35配信)